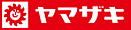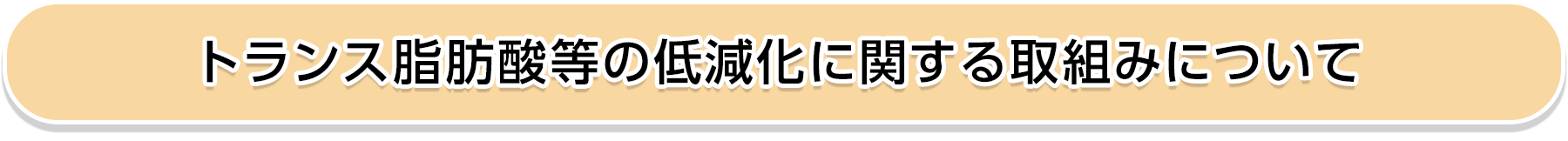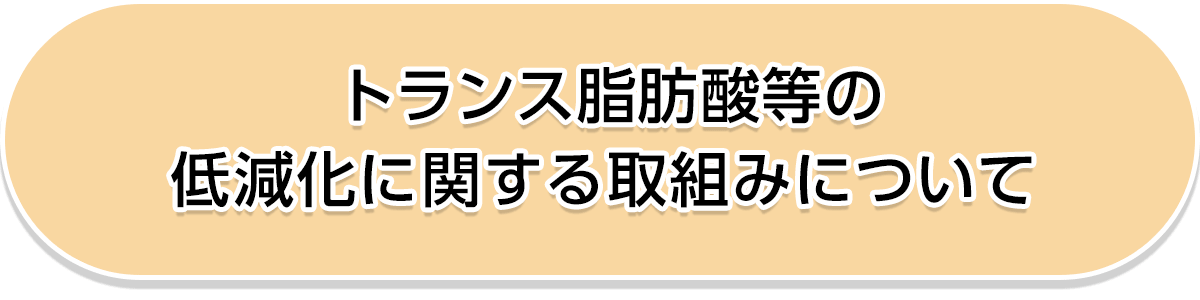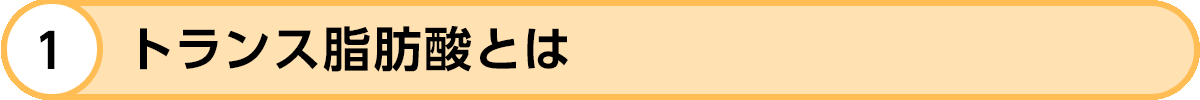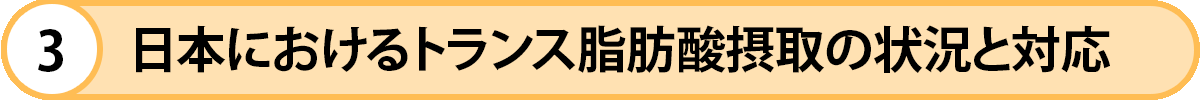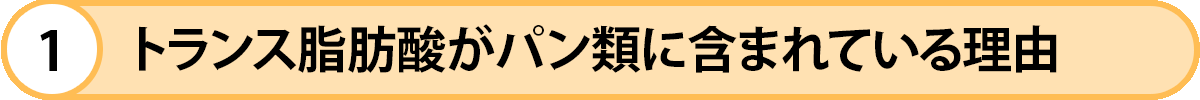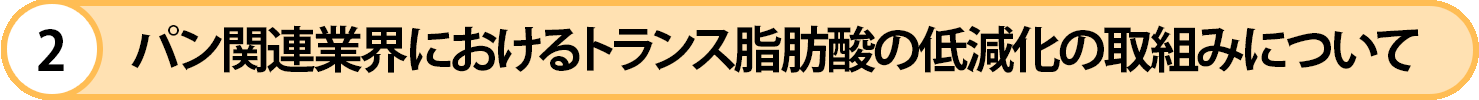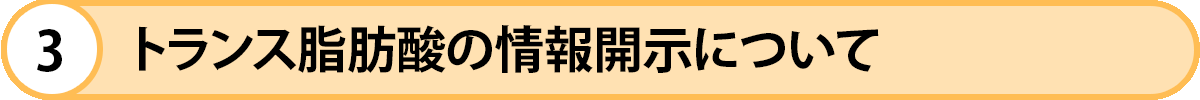Ⅰ トランス脂肪酸をめぐる動き
-
(1)脂肪酸は、油脂などの構成成分ですが、下図の通り、炭素(C)、水素(H)、酸素(O)で構成され、水素原子が結合した炭素原子が鎖状につながった構造となっているものです。脂肪酸は飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分類され、炭素と炭素が2つの手で結び付いた二重結合(不飽和)を一つ以上持っているものが不飽和脂肪酸と呼ばれます。さらに、不飽和脂肪酸は、二重結合の炭素に結び付く水素の向きでトランス型とシス型の2種類に分かれます。水素の結び付き方が互い違いになっている方をトランス型といい、同じ向きになっている方をシス型といいます。天然ではほとんどの場合、不飽和脂肪酸はシス型で存在します。
-
(2)トランス脂肪酸は長期間の過剰摂取により、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)を増やし、HDLコレステロール(善玉コレステロール)を減少させることが指摘されております。その結果として、動脈硬化などによる虚血性心疾患のリスクを高めるといわれておりますが、食生活、食習慣に応じて各国のトランス脂肪酸の摂取状況は大きく差があるとされております。
-
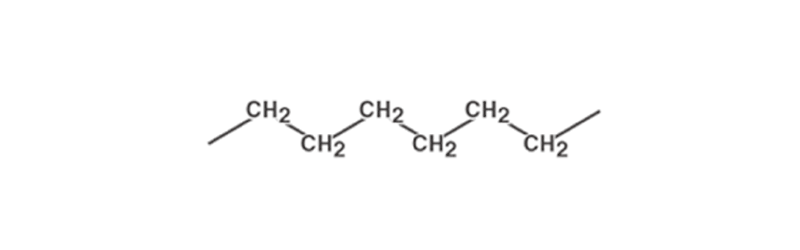
【飽和脂肪酸中の炭素−炭素 一重結合】
-
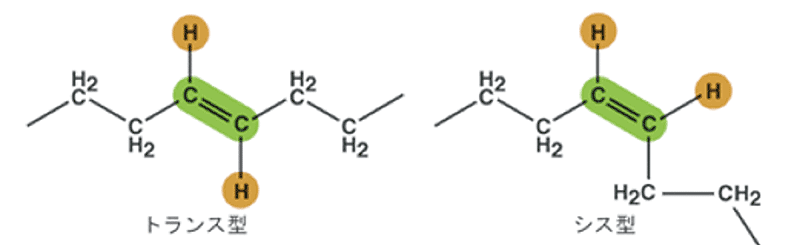
【不飽和脂肪酸中の炭素−炭素 二重結合】
-
(1)WHO(世界保健機関)は、2003年に、「生活習慣病を防ぐために食事から摂る栄養素の量の目標」を公表し、トランス脂肪酸については、総摂取エネルギーの1%相当より多く摂らないようにすることを目標としました。
2018年5月14日、トランス脂肪酸を摂る量の目標とは別に、加工食品を製造するときにできるトランス脂肪酸を減らすための行動計画として、下表の6つの要素からなる「REPLACE」を公表しました。WHOは、各国の政府に対し、この「REPLACE」を使って、2023年までに、加工食品を製造するときにできるトランス脂肪酸を減らすよう呼びかけており、特に部分水素添加油脂の食品への使用規制や食品中のトランス脂肪酸濃度の上限値の設定を推奨しています(その後、2025年までに延長)。
また、2023年には、「飽和脂肪酸及びトランス脂肪酸の摂取に関するガイドライン」を新たに公表し、トランス脂肪酸については、摂る量を総摂取エネルギーの1%に相当する量まで減らすことを強く勧告した他、1%未満に減らすこと、食事中のトランス脂肪酸を他の多価不飽和脂肪酸や植物由来の一価不飽和脂肪酸に置き換えることも推奨しています。これらは、トランス脂肪酸を摂る量を減らすと死亡率や心血管疾患・冠動脈性心疾患のリスクが低減することや、他の不飽和脂肪酸に置き換えると血液中のLDLコレステロールが低減することなどが、複数の研究で示されたためであるとしています。これらの勧告等の対象となるトランス脂肪酸には、天然由来のトランス脂肪酸も含まれます。また、特定の食品の消費を妨げるものではないものの、油脂の加工由来のトランス脂肪酸を多く含む食品を主に避けるべきとしています。REview 加工食品を製造するときにできるトランス脂肪酸について、どんな食品からとっているか、政策を変える必要性があるかを再検討する Promote 加工食品を製造するときにできるトランス脂肪酸を含む油脂の代わりに、より健康に良い油脂を使うことを促進する Legislate 加工食品を製造するときにできるトランス脂肪酸を減らすための法律や規制を制定する Assess 食品中のトランス脂肪酸の量と、人がトランス脂肪酸を摂る量の変化を確認し、評価する Create 政策決定者、食品事業者、消費者に、トランス脂肪酸が健康に与える影響について意識させる Enforce 政策・規制を守ることを徹底させる - (2)国民の脂質摂取量が多い先進国の多くは、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸などを含めた脂質の摂り過ぎについて、生活習慣病の予防のために注意喚起を行っており、バランスのとれた健康的な食生活を推奨しています。また、脂質やトランス脂肪酸の摂取量が多く、生活習慣病が社会問題となっている国では、加工食品中の飽和脂肪酸やトランス脂肪酸の含有濃度の表示の義務付け、部分水素添加油脂の食品への使用規制、食用油脂中のトランス脂肪酸濃度の上限値を設定したりしているところがあります。
- (3)他方、トランス脂肪酸の摂取量が少ない国では、食品中のトランス脂肪酸について、表示の義務づけや濃度の上限値の設定は行わず、事業者に、飽和脂肪酸とトランス脂肪酸の総量を自主的に低減するよう求めているところがあります。
-
(1)トランス脂肪酸摂取の状況
農林水産省は、2005~2007(平成17~19)年度に実施した調査研究で、日本人が食品から摂取しているトランス脂肪酸の1人1日当たりの平均的な量は、0.92~0.96グラムであると推定しました。これは平均総エネルギー摂取量の0.44~0.47%に相当します。 食品安全委員会は、2012(平成24)年3月に、「食品に含まれるトランス脂肪酸の健康影響評価」の結果を公表しました。この評価では、日本人のトランス脂肪酸の平均的な摂取量について、平均総エネルギー摂取量の約0.3%と推定しており、「日本人の大多数がエネルギー比1%未満であり、また、健康への影響を評価できるレベルを下回っていることから、通常の食生活では健康への影響は小さいと考えられる」と結論しました。すなわち、脂質を控えめにし、いろいろな食品をバランスよく食べるという食生活指針の基本を守れば、トランス脂肪酸によって心臓病のリスクが高まる可能性は低いとされております。一方、日本人でも、食事から摂取する脂質の量が多い場合には、トランス脂肪酸の摂取量も多くなることが報告されています。
厚生労働省は、国民の健康の維持・増進、生活習慣病の予防を目的に「日本人の食事摂取基準(2020)」を定めていますが、脂質に関して、総脂質と飽和脂肪酸の目標量(※1)及び多価不飽和脂肪酸の目安量(※2)の基準を定めています。トランス脂肪酸については、健康影響が飽和脂肪酸に比べてかなり小さいと考えられること等から、目標量は定めていません。ただし、WHOが2003年からトランス脂肪酸の摂取量を総摂取エネルギーの1%に相当する量より少なくすることを目標としているため、厚生労働省もトランス脂肪酸の摂取量を総摂取エネルギー量の1%相当より少なくすること、1%相当より少ない場合でも、さらにできるだけ少なくすることが望ましいとしました。- ※1 生活習慣病の予防のために現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量。
- ※2 一定の栄養状態を維持するのに十分な摂取量。
調査年 摂取量(g/人/日) 一日当たりの総エネルギー摂取量に占める割合(%) 米国 2009~2010年 2.5 1.1 カナダ 2008年 3.4 1.42 EU 1995~1996年 男1.2~6.7
女1.7~4.1男0.5~2.1
女0.8~1.92004年 - 1~2 日本 2006/2010年 0.7 0.31 - (注)
- 食品安全委員会「食品中に含まれるトランス脂肪酸」評価書(2012年3月)より
ただし、米国、カナダは内閣府食品安全委員会資料「脂質の摂取~トランス脂肪酸を理解するために~」から引用 - (参考)
- 食用加工油脂の国内生産量からのトランス脂肪酸摂取量の推計:
総エネルギー摂取量の0.7%(1998年)、0.6%(2006年)、0.7%(2008年)
-
(2)食品事業者・国の対応
日本では、日常摂取する主なトランス脂肪酸は、以前はマーガリン、ショートニングなどの硬化油、脱臭のためシス型不飽和脂肪酸を200℃以上の高温で処理した食用植物油に多く由来しておりました。
しかし、最近では、食品事業者による自主的な努力によって、トランス脂肪酸の濃度がこれまでよりも低い食品が販売されています。天然にある乳や反すう動物の肉などに由来するトランス脂肪酸を減らすのは難しいと考えられていますが、油脂の加工工程でできるトランス脂肪酸は、新たな技術を利用することで減らすことができます。食品としての好ましい品質を維持するとともに、飽和脂肪酸を増やさないようにしながら、食品事業者は油脂の加工工程でできるトランス脂肪酸をできるだけ減らすための対策を進めています。
こうしたことにより、農林水産省が、令和4-5年度に市場に流通する油脂類や、油脂を原材料とする加工食品を調査した結果、平成18-19年度や平成26-27年度に調査した結果と比較して、トランス脂肪酸の濃度が低くなっている傾向にあることが確認できました。
なお、日本では、食品中のトランス脂肪酸について、不飽和脂肪酸や飽和脂肪酸、コレステロールなどの他の脂質と同様に表示の義務や基準値はありませんが、冒頭にあるように、消費者庁は、2011(平成23)年2月に、「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」を公表しました。この指針では、食品事業者に対して、トランス脂肪酸を含む脂質に関する情報を自主的に開示する取組を進めるよう求めています。
Ⅱ トランス脂肪酸とパン類
パン類の原材料として使用されるマーガリンやショートニングなどの油脂には、大豆、菜種、とうもろこし、パームなどの植物に由来するものと、バターやラードなどのように動物に由来するものとがあります。これらの中で最も一般的に油糧原料として使用されている大豆、菜種、とうもろこし由来の油脂は常温で液状であることから、パン製造に適するよう固体状にしたマーガリンやショートニングが必要となります。この固体化した油脂は、①油脂の融点が高くなることにより油っぽさを低下させるなどの固化特性の向上、②優れた酸化安定性の付与、③油脂結晶の微細化の促進等により、サクサク感、コク、しっとり感など特有の物性を付与します。特にデニッシュペストリーやドーナツなどの製品では、この油脂の物性が必要となります。この硬化油の製造過程において、水素添加した場合、不飽和脂肪酸が飽和脂肪酸に変化する反応と同時に副反応として、シス型で存在していた不飽和脂肪酸の一部がトランス型の不飽和脂肪酸へ構造が変化することが知られております。
なお、動物に由来するトランス脂肪酸は、反すう動物の胃の中で微生物により生成され、乳製品、肉などにふくまれていることから、パン類にはバターなどに由来するトランス脂肪酸も含まれております。しかし、工業由来と反すう動物由来のトランス脂肪酸では、重複した脂肪酸組成を示すため、それらを分析上で判別する手法は現段階では確立しておりません。
油脂業界ではトランス脂肪酸に対する健康への影響の懸念から、平成10年代より低減化の検討を進めた結果、現在パン類の原材料として使用される多くの加工油脂製品で大幅なトランス脂肪酸量の低減化が図られています。トランス脂肪酸量低減に採用される代表的な手法としては、エステル交換技術、分別技術、結晶調整技術などが知られています。以下には、トランス脂肪酸が含まれる主な加工油脂原料での低減化の取り組みについて紹介します。
-
(1)マーガリン・ショートニング
デニッシュペストリー用の折り込み油脂やパン生地への練り込み油脂として、またバタークリーム用などとして使用されるマーガリン・ショートニングに求められる主な機能は、微細な結晶構造で滑らかな性状や可塑性を有することです。エステル交換技術によりトランス脂肪酸の低減化を図り、得られた融点の異なる油脂を組み合わせて使用することで、従来のマーガリン・ショートニングが有していた広い温度域での良好なスプレッド性やクリーミング性を、また折り込み用シートマーガリンでの伸展性を付与できるようになりました。その結果、以前はこれらの油脂原料中のトランス脂肪酸量は20%を超えていたものが見られましたが、現在は1%以下~5%程度まで低減が図られております。 -
(2)ドーナツ用フライオイル
ドーナツ用フライオイルについては、他の油脂原料とは異なり長時間170~180℃という高温に晒されることから酸化や風味劣化に対する安定性、ドーナツは重量に占めるフライオイルに由来する部分の割合が多くなることからドーナツに相応しい風味、また日持ちが求められるドーナツでは製品が硬くなるのを最小限に止めるなどといった機能が必要となります。現在では、トランス脂肪酸を低減させて品質の維持を図るため、飽和脂肪酸を多く含むパーム油使用比率を高め、分別技術・エステル交換により酸化安定性の劣るリノール酸やリノレン酸等の多価不飽和脂肪酸量の比率を低くしております。その結果、ドーナツ用フライオイルでのトランス脂肪酸量は、以前は20~30%近く含有されていましたが、現在は平均2%以下のレベルまで大幅な低減が図られております。 -
(3)ホイップクリーム
硬化油に由来するホイップクリームの油脂原料については、良好な起泡性・保型性の付与といった機能が必要となります。現在では、ホイップクリームとしての品質を維持し、トランス脂肪酸を低減させる手法として、分別技術、エステル交換技術、結晶調整技術などの様々な技術を組み合わせております。その結果、現在使用されているホイップクリームのトランス脂肪酸量は2~3%台となっております。 - ※ 食品安全委員会と農林水産省は、食品中のトランス脂肪酸、脂質の濃度調査結果について公表(平成18年度は食品安全委員会、平成19年度、26・27年度、令和4・5年は農林水産省)を行っており、平成26・27年度は、33品目中22品目で平成18・19年度よりトランス脂肪酸濃度が低い傾向となっております。また、令和4・5年度の調査では、過去の調査結果と比較して、トランス脂肪酸が全体的に減少傾向にあり、飽和脂肪酸には大きな変動が見られませんでした。
| 値は中央値 (カッコ内は範囲) |
脂質(g/食品100g) | トランス脂肪酸(g/食品100g) | ||||
| H18・19 年度 |
H26・27 年度 |
R4・5 年度 |
H18・19 年度 |
H26・27 年度 |
R4・5 年度 |
|
| 食パン | 4.1 (2.8-6.0) |
3.6 (2.5-5.3) |
3.7 (2.0-14) |
0.077 (0.029-0. 32) |
0.03 (0.02-0.15) |
0.03 (0.03-0.16) |
| クロワッサン | 23.0 (17.1-26.6) |
27 (24-30) |
24 (20-31) |
0.82 (0.29-3.0) |
0.54 (0.22-2.6) |
0.20 (0.12-2.3) |
| 菓子パン | 12.3 (2.9-20.2) |
14 (6.3-21) |
13 (3.8-27) |
0.27 (0.039-0.78) |
0.18 (0.04-0.42) |
0.08 (0.04-0.23) |
| マーガリン | 82.6 (81.5-85.5) |
83 (81-87) |
82 (81-86) |
8.7 (0.36-13) |
0.99 (0.44-16) |
0.65 (0.33-1.3) |
| ショートニング | 100 | 100 | 100 | 12 (1.2-31) |
1.0 (0.46-24) |
0.61 (0.52-0.86) |
| デニッシュ | 19.5 (13.4-22.4) |
19 (14-29) |
15 (13-21) |
0.49 (0.41-0.98) |
0.27 (0.08-3.1) |
0.14 (0.12-0.27) |
(農林水産省「食品中の脂質とトランス脂肪酸濃度」より引用)
当社では、トランス脂肪酸等に関して入手できる情報をホームページにより提供してまいります。特に関心の高いトランス脂肪酸につきましては、角型食パン、山型食パン(食パン)、あるいはあんパン、クリームパン(菓子パン)などの同じカテゴリーに属していれば含有量に大きな差がないため、製品個々への表示ではなく、ホームページでの製品分類ごとのデータにより十分情報提供が図られるものと考えております。
当社では、今後も引き続き製品中のトランス脂肪酸の低減化を進めていくとともに、できる限り情報提供を行っていくことが、お客様のご要望にお応えし、安心してパン類を食べていただくために重要であると考えております。そのため、ホームページ上に代表的なパン類のトランス脂肪酸、飽和脂肪酸、コレステロール及び一般栄養成分の情報を掲載いたします。
パン類に含まれる脂質は私たちの身体にとって重要な栄養素です。また、特にデニッシュペストリーを含む菓子パン類やドーナツなどは、伝統的に脂質成分の働きによって一層おいしさや好ましい食感が引き出され、本来それを楽しむことに価値があるとされる食品です。個々の食品が持つ価値の多様性をご理解いただき、当社の栄養成分に関する情報をバランスのとれた食生活に配慮していくための目安としてご活用ください。
「主なパン類のトランス脂肪酸、飽和脂肪酸、コレステロール等の含有量」
ここで掲載している情報は2024年10月現在のものです。栄養成分情報は定期的に更新いたしますが、使用原材料の変更や製品の改廃などにより、ご案内の内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ※ トランス脂肪酸等の分析について
ホームページに掲載のトランス脂肪酸の数値は、使用している原料油脂メーカーの情報に基づいて算出するか、または当社が独自に製品を分析して算出したものです。また、飽和脂肪酸及びコレステロールについては、一部は日本食品標準成分表に基づいているものもありますが、トランス脂肪酸と同様の方法によって算出しております。
なお、トランス脂肪酸の分析は主にAOAC 996.06(AOACインターナショナル公定法)または、基準油脂分析試験法 2.4.4.3-2013(旧 暫17-2007)(日本油化学会の提唱する分析法)により行っております。